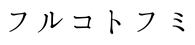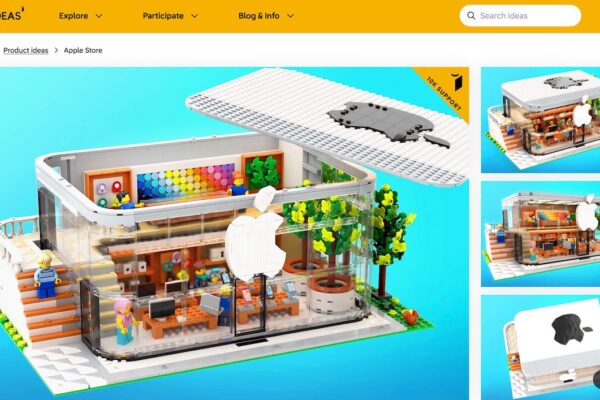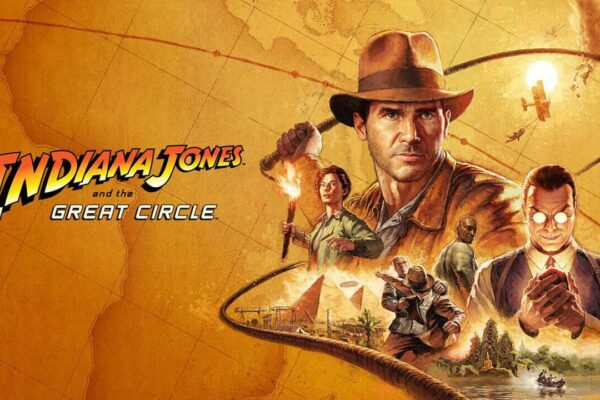米国政府機関閉鎖について。
米国政府機関閉鎖は過去最長に | 木内登英のGlobal Economy & Policy Insight | 野村総合研究所(NRI)『』
前にも、トランプ氏が大統領に就任した頃に同じようなことがあった。
あの時は日本にいて、「アメリカは大変だなあ」と、どこか対岸の火事のように眺めていた。
正直、自分には関係のない遠い出来事だと思っていた。
ところが、今回はそうはいかない。
いまはこの国の中で生活している。
ニュースで「政府機関閉鎖」という文字を見るたびに、
「これは自分にも何か影響があるのでは」と落ち着かない気持ちになる。
それでも街の様子は意外なほど静かで、
スーパーも開いているし、郵便も届く。
ニュースほど切迫した雰囲気はない。
人々もどこか慣れたような表情で、
淡々と日常を続けているのが印象的だ。
ただ、その水面下では確実に波紋が広がっている。
たとえば、ただでさえ時間のかかるグリーンカードの申請。
今回の閉鎖で、DOL(労働省)の業務が一か月近く止まってしまった。
ようやく最近になって部分的に再開したらしいが、
完全に元通りというわけではない。
積み上げられた書類の山を想像すると、
ため息が出そうになる。
正直なところ、勘弁してほしい。
それでも、こうした混乱の中でも制度や手続きを守ろうとする姿勢には、
一種の信念のようなものも感じる。
「現実的に動く」ことを重んじるこの国でも、
譲れない原則はやはりあるのだと気づかされる。
実用主義の国、プラグマティズム誕生の地であっても、
根っこのところでは理想や信念が息づいているのかもしれない。
いやこれこそがプラグマティズムなのか。
そう考えると、少しだけ感心してしまう。
けれど、それはそれとして早く再開してほしいというのが本音だ。
書類が動かない間にも、生活は進むし、時間も過ぎていく。
結局のところ、自分にできるのは待つことだけ。
ニュースを見ながら、ふと外に目をやると、
いつもと同じように子どもたちの声が聞こえてくる。
閉鎖と日常が、どこかで同居している不思議な光景。
それでも、今日も一日は過ぎていく。